
長崎西高の個性豊かなOBの方々をご紹介する【WOW! 】 へようこそ!編集部の本多です。今回は34回の宮地勘司(みやじ・かんじ)さんにお話をうかがうことができました。 僕らからは考えられないくらい自由な高校生活にはじまり、社会人になってからのご活躍まで、たくさんお話を聞かせていただきました。
・高校生活、大学生活、イマイチ周囲になじめない!と思っている人
・遊んでそうとか言われるけれど、実は読書や新聞、哲学が好き!という人
・起業や新規事業に興味があるという人
宮地勘司さんのプロフィール
パンチパーマで入学式!? 高校生時代を振り返って
ーー(本多)本日はありがとうございます。まずは中学生、高校生の頃のことを教えてください。
(宮地さん 以下敬称略) 松山町の平和公園の向かいに父が経営する寿司屋があって、その近くに住んでいたので、小学校は城山小学校でした。本来なら淵中学校に進学するはずだったのですが、その頃、父が生家のある神ノ島に家を建てて引っ越したので、西泊中学校に進んだんです。中学時代は、周りにやんちゃな子が多くて、一緒にダブダブのズボンをはいていきがってみたり、バンドを組んで文化祭で演奏したりしていました。高校に入るときには「なめられちゃいけない」と思って、パンチパーマにしてから入学式に行きましたね。
ーーパンチパーマで!僕らの時代からすると考えられません(笑)高校生活はどうでしたか?
(宮地) 校ではラグビー部に所属しました。ラグビーなら高校から始める人も多いので、ディスアドバンテージがないかなと思って。たまたま私のポジションが空いていたので、高校二年生のときに正規メンバーに入れてもらったのですが、先輩の代が名選手が多かったので、県大会の決勝まで行ったんですよ。「勝てば花園」というところまで行ったところで、長崎南高に負けてしまって悔しかったのだけれど、その南高も、全国大会であのスクールウォーズにもなった伏見工業とあたって、完封負けしていました。
そんなふうにラグビー部でがんばったり、友達も多くて、まじめな生徒ではなかったけれど、楽しい高校時代だったなと思います。 授業には遅刻をしたり、学校を途中で抜け出して友達とお好み焼きを食べに行ったこともありました。そんな生徒だったので、数年前に高校時代の同窓会で当時の先生に会って、私の会社 (教育と探求社) の 名刺を渡したら『お前が教育?!不良やったお前がか!?』とたいそう驚かれたんですよ(笑)
ーー大学受験はどうでしたか?
とにかく東京に行きたくて、受験勉強にも精を出しました。その結果、共通一次は800点以上とれたのですが、二次試験がだめで浪人となって。でもどうしても東京に行きたかったので、「どうせ浪人するなら東京でやったほうがいい」と親を説得して東京に出してもらいました。 早稲田大学に行きたいと思って受験したんですがすっかり合格したつもりになって、高田馬場に一本で行ける西武新宿線沿いに早々にアパートを借りたのですが、駄目でした。思い込みが強いでよね、この頃から(笑)
結局、明治大学と立教大学には合格して、立教大学に行きました。実家が長崎で外食店をいくつかやっていたので、外食サービス業について学べる立教大学の観光学科にしたんです。
『明日からウチで働きなさい』板橋のスナックで過ごした大学生時代
ーー学生時代のことを教えてください。
(宮地) 大学に通いはじめてみたら、そのとき自分には思ったより面白くありませんでした。田舎者で気後れしていたこともあって、大学で縁ができなくて(笑)しばらく講義やサークルにも参加せずに過ごしていたら、西高時代のラグビー部の同級生が「上板橋の駅そばにあるスナックに連れて行ってくれました。
そのスナックは、つい少し前まで銀座のクラブで働いていた女性が地元に帰って新しく始めたお店でした。スナックに集まった人たちと、話したり歌ったりするうちに、なんだかとても気に入られて。「あんたおもしろいから明日からここで働きなさいよ!」なんてスナックのママが言うもんだから、「わかりました!」って即答して、その翌日からお店の2階の6帖間を借りて、住み込みで働き始めました。
ーーそれはすごいですね!今の僕らからしたら考えられません。
(宮地) 実家が料理屋だったので、包丁を使えるし、仕込みもできるし、スナックで私は「チーフ」と呼ばれていました。店を閉めるときには私が「そっとおやすみ」を歌うのが定番で、毎日それを歌って片付けて、気づけば深夜の1時2時という日々でしたね。
大学に行く暇はまったくなくて、「大学はもう辞めちゃおうかな」とも思いました。漠然と「家業を継ぐのかな」という思いもあったし、店のママからは「お金を出してあげるから、弾き語りの学校に行きなよ。チーフなら自分のお店を持てるよ。」なんて言ってもらったこともありました。
ーー本やマンガの中の学生生活みたいですね!その後はどうされたんですか。
(宮地) 大学3年になった頃、大学の友達から「そろそろ大学に戻って来いよ。」って熱烈に言われて、そこから大学の勉強を頑張りはじめました。1年生の修得単位は5単位、2年生は0単位、3年生で49単位。こりゃ卒業はむずかしいな、と思っていましたが、友達の支援があったので、奮起しました。
「4年生で95単位とれば卒業できる」と、月曜から土曜日まで、朝一から夜の7時近くまでびっちしと履修をしました。その結果、91単位取ったんだけど、あと1教科、4単位どうしても足りなくて。一般教養課程の「行動科学のための基礎数学Ⅰ」という教科です。他の教科名なんて覚えてないけど、これだけは忘れられないですね。なんとかならないかと先生の研究室を訪ね、土下座する勢いで頼み込んだけどダメでした。「あちこちでそんなこと言って単位稼いでいるんだろう」みたいに言われて(笑)結局あきらめてもう1年通って、5年で卒業しました。
『冗談だろ?!』友人みんなが驚いた就職先は、「日本経済新聞」
4年生で95単位とれば卒業できると月曜から土曜日まで、朝一から夜の7時近くまでびっちしと履修をしました。その結果、91単位取ったんだけど、あと1教科、4単位どうしても足りなくて。一般教養課程の「行動科学のための基礎数学Ⅰ」という教科です。他の教科名なんて覚えてないけど、これだけは忘れられないですね。なんとかならないかと先生の研究室を訪ね土下座する勢いで頼み込んだけどダメでしたね。「あちこちでそんなこと言って単位稼いでいるんだろう」みたいに言われて(笑)結局あきらめてもう1年通って、5年で卒業しました。
ーー就職活動はどうされたんですか?
(宮地)もともとちゃんとした企業に入りたいとも、入れるとも思わず、「おれはクリエイターになる!」とか根拠もなくうそぶいていました(笑)
ただ、親の影響もあり、ビジネスには興味があったので、日経(日本経済新聞)は受けに行ったんですよ。まず最初が筆記試験で、これがそこそこ難関なのですが、好きで日経新聞は毎日読み込んでいたので筆記試験は比較的よくできました。次に英語、これは苦手だったのですが、ちょうどチェルノブイリの事故があった年で、その英文記事が出題されたんです。日本語の記事でそれはよく読んでたから、ラッキーにも内容が全部わかりました。
結果、筆記の成績は上位でしたね。中学生くらいのころから読書は好きで、大学生活で遊んでいた時も、本と新聞だけはめちゃくちゃ読んでました。ギリシャ哲学とか物理学とか文化人類学とか、自分にとってはすごく面白かったんです。大学では「遊んでばかりいる先輩」だったから、日本経済新聞に就職することになったときは後輩たちにもひどく驚かれて、「奇跡の日経 」 なんて言われました。
新聞社の仕事は肌に合い、とても楽しかった
ーー日経新聞でのお仕事のことを教えてください。
(宮地) 日経には16年半いました。 広告局に配属されて、日経流通新聞、今のMJに配属。仕事は面白かったです。新聞社では、やりたようにやらせてくれて、2年目にはもう自分が部署を牛耳っているような気分でした。少し傲慢だったと思います(笑)
その後、日経グループのテレビ東京の系列局、テレQ(テレビ九州)の開局で、その東京支社に出向しました。広告代理店に入社していた友人が、「ローカル局の営業は大変だよ。やりがいを見つけることもむずかしいよ」と会社を辞めたほうがいいんじゃないかとまで言われました。実際、彼が言うとおりで、全国にテレビ局は400局以上あって、クライアントはどの局にいくらCM出すなんてそれほど細かく考えていないので、ローカル局はクライアントではなく広告代理店に営業することになるんです。広告代理店に営業にいくと、もちろん人によってですがひどい対応をされることもあって、料金交渉しにいくと「いいからやれよ〜、ローカル局なんだから!」と言われることもありました。私も若気の至りで「ビジネスでそんな口のきき方って、どういうことですか!?」とか、よく言い返していましたね。
そんなある時、日経の同期の結婚式で余興を頼まれて。披露宴で衣装を作って歌いました。オヨネーズの「麦畑」。かつらから衣装までこさえて、左半分をオトコ、右半分をオンナにして、右向いたり左向いたりしてひとりで歌い切りました。それが参列していた日経の偉い人の目に止まったみたいで、急きょ予定より早く日経に呼び戻されました。あとから聞いたのですが、これから景気が下り坂になるときには、あんな破天荒なやつが必要だという理由らしいです(笑)
ーーそんなことがあるんですね(笑)
(宮地)それからは、広告2部という部署にいきました。新聞社では“ナンパ”と呼ばれる業種なのですが、お酒とか、食品とか、レジャー・サービスとか、消費財形の広告を扱う部署ですね。その部署に10年いました。その時に新聞協会賞を受賞したこともありましたね。団塊の世代が50代になったときに、子育ても終えて、これから消費のリーダーに躍り出てくるという潮流を抑えた企画です。吉田拓郎とか、矢沢永吉とかがバーンと新聞の一面に載った別刷り企画でした。
2000年には、日経の労働組合の執行役員を任されました。組合は、将来役員になるには必須のキャリアと言われていたので、嬉しかったですね。新聞社は職種のデパートと呼ばれていて、政治経済記者や科学記者などの頭のいい人たちもいれば、販売や広告などビジネスが得意な人、夜中に新聞を印刷する人たちもいる。部署が違えば違う会社みたいなもの。なので40歳前後で組合をやることで、他部署の具体的な仕事の内容や働く人々の歓びや苦しさを知り、経営という観点で新聞社の財務状況や経営環境を分析することはとても勉強になりました。
2001年に組合から新聞の仕事に戻ったんですが、5月のある日、夢を見たんですよ。当時日産を危機から立て直したばかりのカルロス・ゴーンさんと、彗星のごとく現れたユニクロの柳井さんがふたりで熱っぽく話をしている夢。「ビジネスって最高に面白い。人生ってダイナミックだ 」って。 それをすごい数の高校生たちが、キラキラした目で見てるんです。すぐに飛び起きてメモしました。高校生のためのビジネススクール。これはおもしろいと思いました。
夢で見た景色が忘れられなくて 教育事業へ
ーー夢で!それはまたすごい話です。高校生に向けたキャリア教育などは、最近盛り上がっていますよね。
そうそう。今では普通だけど、当時はそんなものあまりなかった。実際、「キャリア教育」という言葉をその頃の私は知りませんでした。
夢を見た翌日、いろんな人にこの話をしてみたんですよ。高校生が企業のトップからビジネスを学ぶような企画をやったらどうだろう?って。でも周りからの反応は薄いんですよ。なんで高校生?なんで教育?もうからなさそうだね、ッテ。
うーんと思って、当時グループ会社の社長だった方と食事をする機会があって、よし、ここだと。夏休みは新聞の広告って、出稿する企業が少なくてカラカラになるんです。それでその社長と会食の時に、「高校生のためのサマースクール企画を企業協賛の形で実現できないだろうか」と相談したんですよ。そしたら「それは面白い!俺と一緒にやろう。 」と言ってくれて。すぐにその場で 紙ナプキンに参加してくれそうな企業をリストアップし始めたんです。それからもなんやかやと反対する人もいましたが、社長と私でやりたいという企業を8社集めて「日経エデュケーションフォーラム(その後 「日経エデュケーションチャレンジ」という企画ができたんです。
夏休みに高校生を500人くらい集めて、いろいろな企業のトップが授業をする。高校生は、その感想レポートを書き、優秀作品が新聞に載るという企画。1ページの広告料金は1千万円を超えていますから、8社も集まれば1億ぐらいの売上になる。うまくいきそうだ!と思ったけれども、肝心の高校生が集まらない。日経を使って募集広告をしてもそんなの見てる高校生はいないし、500人の会場に残り2週間位なのに50人くらいしか高校生が集まらない。自分の夢からスタートした企画だけど、これほど多くの人を巻き込んで、絶対に失敗はできないと思い、気がついたら毎日毎日いろんな高校を回って、必死に参加してくれる人を集めました。
最後に、早稲田実業の先生が高い関心を持ってくれて50名くらいの生徒を送ってくれて、250名くらいとなり、どうにかかっこうがついたという状況でした。その後、参加者は増え、今では、もう20年続いている日経の夏の名物企画になっています。
日本経済新聞を退社 経営者として「クエスト事業」を全国へ
ーー20年。それはすごいですね。その後、起業されたということですが、どういった経緯だったのでしょうか?
(宮地)もともと会社を辞めるつもりは全然なかったんです。「日経エデュケーションフォーラム」を立ち上げたことで、新聞社の教育事業の可能性を感じて新規の教育事業をやりたかった。当時、学習指導要領の改訂があり、いわゆる「ゆとり教育」が学校現場で始まっていました。「総合的な学習の時間」がはじまったのもこの頃です。でも現場の先生は困っていました。環境、福祉、国際理解、職業感、自己のあり方生き方を考える授業を先生が自ら考えてつくるとなっていましたが、それはあまりにも先生には荷が重すぎる。そこで私は、日経新聞がつくる「活きた社会科の授業」は可能性があるのではないかと考えました。学校の先生には喜ばれるし、生徒たちも現実社会を楽しく、深く学ぶことができる。日経新聞にとっても、教育を経済報道と並ぶ2つ目の看板にできる。そう思っていろんな人に相談したんです。でも反応は芳しくない。だれも私の考えには荒唐無稽であると耳を貸しませんでした。
そこであるベンチャー企業の社長に相談したんです。そしたら『黒船を出せ』と言われました。妙なことを言うな、と思ったのですが、日経みたいに100年以上、同じビジネスモデルでやってきた会社は、身軽に転換はできない。徳川幕府はペリーが来たから開国したんだ。つまり外圧をつかって日経の役員たちが教育事業を始めざるを得ない状況を作るんだというのです。
私はどうしたものかと思案したのですが、「大手総合電気メーカー社の社長が社内大改革の一つのプランとして、100億円のベンチャーファンドを作り、社員から100名の起業家を出す」という内容の記事が目にとまりました。すぐに電話をかけて教育事業会社を一緒に立ち上げようと持ちかけたところ、一月もたたないうちに1億5千万円の出資をする内定をいただきました。また次に、大手通信会社にも話をもちかけました。当時政府は世の中をすべてIT回線でつなぐe-Japan構想を立ち上げていて、大手通信会社グループが巨大な戦略子会社を立ち上げていたのです。その会社に、「ネット空間に学校を作りましょう」という提案を持ちかけると、1億円を出資する話の検討を進めてくれました。それから、事業計画を作り上げ、日経の副社長に話を持っていったんです。日経が教育事業をやることの意義を語り、その頃には学校での実験授業も終えていたので、その動画も見せて、最後に、出資の内定をいただいている話をしました。副社長は驚いていましたが、すぐに社長に相談して、それで『教育開発室』という部署ができたんです。おそらく現場からの提案で部署ができたのは日経史上でも過去にはないと思われます。結果的に社内起業という形になりました。
ところがその直後に、日経新聞の上層部にスキャンダルがあって。新規事業なんてできる状況ではなくなりました。もはや教育事業を諦めて新聞づくりに戻るか、会社を辞めて、自らの思う教育事業に邁進するか。その選択をしなければならなくなりました。その時41歳、厄年。妻も子どもも二人いたし、家も買ったばかりでローンも山ほどあったし、相当悩みましたね。2ヶ月くらいはずっとこのことを考えていたと思います。 最終的には、今やらないときっと死ぬときに後悔すると思ったんです。やったことの後悔は時間が経てば小さくなるけど、やらなかったことの後悔は歳をとるほどどんどん大きくなるって。60歳、70歳になって、あ〜、あのとき勇気がなかったなと思う人生はいやだと思ったんです。日経新聞を辞めて起業することにしました。
『大人も子供も、細い穴からお互いをのぞいている』
ーー最後に、教育事業への思いと、現役西高生へのメッセージをお願いします。
(宮地)自分の人生を振り返ると、常にアウトサイダーだったなという自覚があります。パンチパーマで高校の入学式に出て、大学ではスナックに住み込みで働いて。吉田拓郎、矢沢永吉、テリー伊藤、田崎真也などを日経で初めて取り上げたり、アウトローな企画ばっかりやってきた。
でも、なぜ、教育を仕事にしたかといえば、人間が可能性を開く瞬間ってのは何にもまさる、感動やすばらしさがあるな、と思って。
大人も子どもも、小さい穴からお互いのことをのぞいているんだと思うんです。大人は子どもをわけがわからんやつらだと見下したり、避けたりすることもあるし。子どもは大人に対してこんな変な世の中をつくりやがって、って怒っていることもある。 でも、その穴をぐいっと広げて見れば、見え方が変わるんですよ。子どもたちは大人が思うよりもずっと真剣に深く物事を考えているし、大人の中にもちゃんとした人たちはいっぱいいる。今の平和で快適な社会をつくってきたのは多くの大人たちのたゆまぬ努力の賜物なんです。それを説教や無理矢理ではなく、互いに知ることができたら素晴らしい社会がはじまるんじゃないかな、ってそう思っています。
実は、今やっているも自分の事業を「教育」とはあんまり思ってないですよ(笑) 相互理解や越境体験を通して自らの意識を広げること。すべての人がそんなふうに学び、豊かに生きていく。そういう社会を目指しています。
ーーマンガやドラマを見ているようなお話ばかりで、エキサイティングでした!ありがとうございました。
【編集後記(55回生 本多)】
『大人も子供も、細い穴からお互いをのぞいている』
この言葉が深く印象に残りました。いわゆる『大人』についての見え方は、高校生の頃の自分と今の自分を比較して、一番大きく変わった部分かもしれません。高校生の頃に僕が想像していた『大人』の像はとても小さかったなと思います。実際はみんな思ったよりも悩んでいるし、子供の頃と変わっていないし、たくさん考えたり、壁にぶち当たったりしている。このメディアを通して、そんな大人のリアルな姿を少しでも知ってもらえたらいいなと思います。
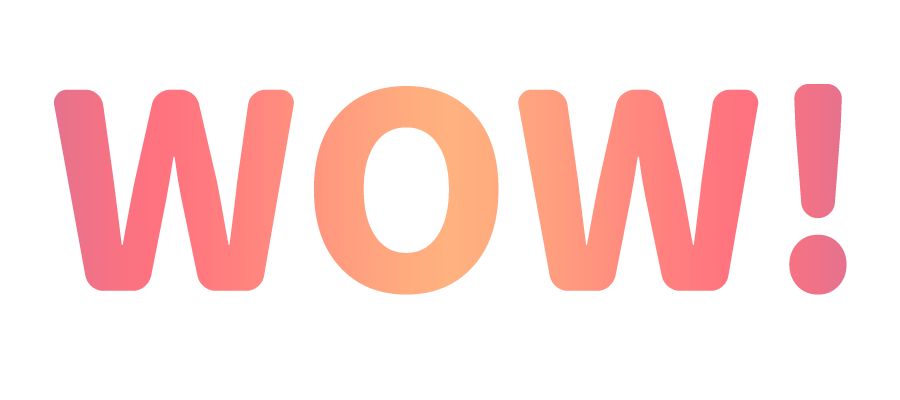


コメント